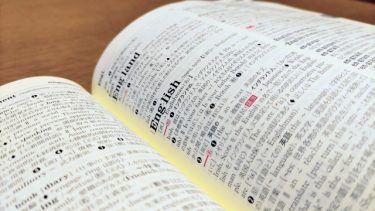なぜ、外国語の習得を難しく感じるのだろうか。なぜ、誤訳が生じるのだろうか。なぜ、日本語のコンピュータ関連の言語環境は、世界と比べて遅れをとっているのだろうか。それは、言語の構造上の違い、文法の違い、その背景である文化の違いという要因が深く関連している。特に、Google翻訳など、機械翻訳や、ChatGPTなどをはじめとする、AI 人工知能を使った翻訳機の精度がイマイチなのは、日本語と英語の文法構造上の違いが大きい。そこでこの記事では、その中心的な原因とも言える、主語の概念の違いについて考えたい。
日本語での根本的な英語との違い
日本語の独特な文法構造について、三上章の著書「象は鼻が長い」では興味深い主張がなされている。その中心となるのは、「日本語には主語がない」という考え方だ。極端な表現だが、「英語の主語と日本語の主語では性質が違う」という意味であり、この考え方は、日本語の理解と使用において、根本的な欧米語との違いを示唆している。
「は」の使い方に注意
日本語では、通常「XXは」と表現される部分が、英語でいう「主語」ではなく、「主題」または「トピック」として機能する。しかし、このことは長い間広く理解されてこなかった。「は」は、話題を提示する際の枠組みを提供するものであり、文の最後の部分までかかる。一方で、「XXが」という表現は、より主語に近い役割を果たす。だが、これもまた一義的ではないので、文脈によって使い分けられなければならない。
例えば、
「象は鼻が長い」
という文章の主語はなんだろうか。多くの人は「象」だと思うかもしれない。しかし、文法的に厳密に考えた場合、この文の述語は「長い」であり、その対象は鼻であって、象ではないので、「象」が主語とは言えない。
少しわかりやすくするために、
「象の鼻は長い」
と言い変えてみると、主語が「鼻」であることが鮮明になる。「象は鼻が長い」においては、象は主題であり、全体のトピックであり、主語はあくまでも「鼻」だと分かる。
「象」が主語だと思ってしまうのは、英語の影響も多分にあるかもしれない。英訳すると、
Elephant has a long trunk. (象は長い鼻を持つ)
となり、やはり象が主語だと思われる。しかし、「持つ」という動詞は原文の日本語にはない。だからこう意訳するしかないのだが、あえて原文に忠実に訳すとどうなるか?
As for Elephant, the trunk is long.(象について言うと、鼻が長い)
つまり「鼻」が主語であって、やはり、この文において、「象」は、主題・トピックということで落ち着くと思う。
「は」はいろんな役割を兼務する
こう見てくると、面白いことに、日本語においては、この「は」が曲者で、いろんな役割を兼務している様子が浮かび上がってくる。ある時は、動詞の意味も隠し持っていたり、さらに視点を変えると、「の」の役割も果たしていることが分かる。英語に訳す時には、この「は」が何を表しているのかをよく観察しながら作業を進めないと誤訳してしまうので、注意が必要だ。
三上は、日本語と欧米の言語との間に存在するこのような根本的な違いから、「主語」という概念を適用すること自体が不適切であると主張している。日本語は欧米語とは全く異なる系統に属する言語であり、その文法や表現は独自の論理に基づいていることを、私たちは踏まえなくてはならない。
主語の性質の違いが与える影響
流暢さの問題
この日本語の言語的特性は、特に翻訳や英会話や、さらに外国人の日本語学習における障害となって顕著に現れる。日本人が英語を話す際には、文の主体を明確にするために、無意識のうちに「主語」を探す作業を行われ、ここに時間がかかってしまい、流暢さを失ってしまうことにつながっている。
日本語学習の問題
逆に、英語などの欧米言語を母国語とする日本語学習者にとっては、「は」と「が」の使い分けなど、日本語特有の文法規則に苦労することになる。
人間主体 vs 無生物主語
さらに、主語について意識し始めると、英語と日本語では大きくその概念自体が違うことが観察される。日本語では、人間が主体の文章構造が多い。一方で、英語には、無生物が主語になる場合が多くある。例えば、英語では「it」を主語として使用し、さまざまな事象を説明する表現が多く存在し、これは日本語にはあまり見られない特有の表現である。
無生物主語をマスターできれば、自然な英語を作る達人となれるだろう。だが、そういう発想がない多くの日本人には難しい。翻訳機を使うにあたっても、英語学習にも障害になる。その一端を観察するために、Business, Morning, Challengeなどを取り上げて考察した。
翻訳に与える影響
このような言語間の違いは、Google翻訳などの機械翻訳ツールを使用する際にも影響を及ぼし、誤訳の原因となることが多々ある。その間違いを追求していくと、この問題に突き当たる。誤訳を正すには、「誰が」という主体を明らかにしてあげることで解決に向かう。詳しくは、別記事を参照して欲しい。
ChatGPTが翻訳もできるようになった。その実力は、英訳に限って言うと、まだまだそのまま誰かに読んでもらえるレベルではなく、2つの言語に精通する人にチェックしてもらわないと使い物にならない。しかし、その速さは抜群である。使い方さえ工夫すれば、色々と使い道が考えられ、有益な道具となるだろう。
スピーチでは主体が誰かを常に意識して話そう
また、スピーチを行う際には、聴衆にとって理解しやすいように、主体やトピックを明確にすることが重要になってくる。国際舞台で活躍する時、自分がわざわざ英語を話す必要はない。通訳を雇ったり、将来的には、通訳機を使えば済むことだろう。しかし、ここで注意が必要だ。常に、誰が主体なのかをはっきり話すようにする。そうすることで、翻訳機が間違えないようになる。人間サイドで気を使ってあげることが必要だ。
三上章の指摘は、言語を通じて文化や思考の違いを理解する上で貴重な洞察を提供しており、今日のグローバル社会においても、日本語と他言語との間に存在する深い溝を橋渡しするための一歩となっていると思う。
日本語には「当たり前」な部分は省略される性質があり、これは文法的な機能であり、仕方のないこと。しかし、それが論理思考に影響することを認識することが大切だ。なぜなら、それを意識することで、より分かりやすい英文を書くことができ、外国人とのコミュニケーションがよりスムースになるからだ。
日本人が英語に書く時、受動態を使いがちだ。それは、文化的な背景や文法的な背景。特に日本語には主語が省略されがちなことや、無生物主語を主語にあまりしないことが起因している。それを踏まえて英語を学習し、翻訳機械を使いこなすことで、異文化コミュニケーションが円滑に行われるだろう。
役職が上がると人前で話す機会が増える。しかし、それが思ったようにうまくできなくて悩む人は多い。スピーチ・プレゼンがうまくできる人は、みなそのテクニックを駆使している。そのテクニックさえマスターしてしまえば、そんなにスピーチで悩む必要はなくなるものだ。
スピーチ学習は、あなたの人生や仕事の質を劇的に変えるものなので、ここに思い切って自己投資することは大いに意味があることだ。どのスピーチ講座が自分にぴったりなのかを選ぶためにはは、自分のニーズ・目的・価値観をクリアにした上で、比較検討し、自分のレベルに合わせたものを選ぶのが賢明なやり方だ