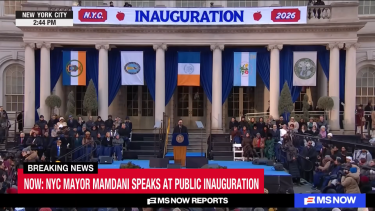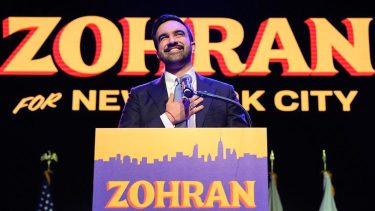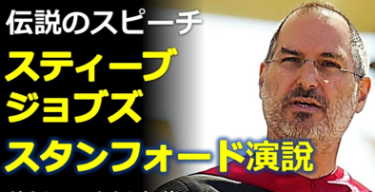”信元夏代のスピーチ術” 編集長、プロフェッショナルスピーカーの 信元です。
去る5月25日、テレビ朝日の番組に信元が出演し、約40分にわたり、大谷翔平選手の4つのスピーチを解説しました。
大谷選手のスピーチを何度も見ていた中で、他のアスリートたちのスピーチなども見ていったのですが、調査分析している中で気づいた点があります。
それは、秀逸だと取り上げられるアスリートのスピーチには共通項があるということです。
今回は、大谷翔平選手とイチロー選手のスピーチを取り上げて、3つの共通項について解説していきます。
1.聞き手視点とYes AND
2024年5月末、シーズン前に大谷選手が移籍する噂が流れたブルージェイズとの一戦があり、大ブーイングの中、大谷選手は先制ソロホームランを放ち、勝利に貢献しました。その試合後のインタビューで、ブーイングについて尋ねられた時の回答が秀逸でした。
自分のチームが好きだからこそ、相手の選手にブーイングするんだと思う。
そういう熱量は、ドジャースファンでもブルージェイズファンでも、野球が好きなんだなというリスペクトを逆に感じる。
結果的に僕はブルージェイズにノーと言っている。僕がブルージェイズのファンだったら普通にブーイングすると思う。
それは野球の一環ですし、ファンの人たちが楽しいのが一番だと思う。
自分視点のメッセージでは、「伝えた」と思っていても「伝わった」状態にはなりません。「伝えた」と「伝わった」は別物です。
「伝わった」という状態に持っていくためには、聞き手は今どんな心理状態にあるのか、まで考えたうえでメッセージを構築するのが、成功するスピーチのカギになります。これが「聞き手視点」です。
ともすると、「ブーイングはやはり(自分にとって)プレッシャーになりますよね」、あるいは、「(自分は)ブーイングは気にしないようにしています」と、「自分視点」で話してしまいがちですが、この時の大谷選手のスピーチは、敵意を持っているかもしれないファンの立場になるという、「聞き手視点」で話したことが大きなポイントです。
大谷選手から学びたい、好感度を爆上げするコツ
更に言うならば、この「聞き手視点」の中に、「Yes AND」のマインドが入っている、というのも、大谷選手の人柄はもちろん、彼の信念までが見え隠れし素晴らしい点です。
この、「Yes AND」とは、肯定で受け止める、ということです。「はい、そして」と呼んでいる手法です。困る質問とか反論を受けても、「いやそうじゃなくて」と、否定で返すのではなくて、「Yes」と肯定で受け止めて、「AND」そして、とプラスで乗せていくんです。大谷選手はブーイングさえYesで肯定して、「でも」ではなくてAND、「リスペクトを感じる」とポジティブに変換しました。この点も素晴らしいです。「野球が好きなんだなというリスペクト」というのはなかなか瞬時には出てこないですよね。
「Yes AND」のマインドを持った話し方は、どんな聞き手からも好感度を持たれることでしょう。
そして、イチロー選手も「聞き手視点」に優れていて、中でもイチロー選手の引退会見のスピーチは、アメリカ中からも絶賛されたものでした。
イチロー選手の「聞き手視点」づかいは、皆さんも今日からマネできる点があります。それは、「主語を聞き手にする」ということです。
イチロー選手から学びたい、今日から使える聞き手視点のコツ
“The one you got was 27years old, small, skinny and unknown.”
(あなた方が迎えたのは、 27 歳の小柄で痩せた、無名の選手でした)“You had every reason not to accept me. However, you welcomed me with open arms and you have never stopped.”
(あなた方が私を受け入れない理由はいくらでもあったでしょう。けれども、あなた方 は両手を広げて私を迎え入れてくれて、決して止めることはありませんでした。)
もちろんどんな野球選手でも、「これまで私が活躍できたのは、ファンのみなさんのおかげです」くらいは言うでしょう。でもイチロー選手は、自分の引退会見であるにもかかわらず、主語を徹底的に「You」(時には球団の仲間たちのYou、時にはファンの皆さんという意味でのYou)、つまり「聞き手を主語」にすることで徹底した聞き手視点のメッセージを心から伝えたのです。
2.ユーモアの活用
大谷選手が、結婚相手について取材に応じた際のスピーチも反響を呼びました。
「そもそも発表しなくてもいいところをアナウンスしたというのはどういう意図があったか」、という質問に対し、尾谷選手は次のビデオのように回答しています。(3’25″あたり)
ここでのポイントは「一番は皆さんがうるさいので。しなかったらしなかったでうるさいですし」と、ユーモアを交えたことです。
おそらく大谷選手はプライバシーに関わる発言をしたくなかったことが伝わってきますが、その本音をユーモアを使うことで、いやみなく、マイルドにする効果がありました。
アメリカではスピーチの中のユーモアは絶対的に必要です。誰も、面白おかしくもないスピーチを聞くのはつらいじゃないですか。せっかくなら楽しく聞きたい。ユーモアは相手の心の扉を開く鍵にもなります。
ただし、ユーモアではなくジョークを使ってしまうと落とし穴にハマります。
例えば、もし大谷選手が、ジョークのつもりで、
「皆さんがうるさいんで、言わないと野球に集中できないと思って。」
と言ったとしたらどうでしょう。「なんだよ、うるさいって。有名人なら注目浴びるの当然だろ」とへそを曲げる人が出てくるかもしれません。
ユーモアとジョークの違い
ユーモアとジョークの違い、なんだと思いますか?
ビジネスの場において、情報のエンターテイメントであるスピーチ・プレゼンには、ユーモアは大切です。でも、実はジョークは避けるのが得策です。なぜでしょう?そしてユーモアとジョークの違いは何でしょうか?ビジネスでのスピーチ・プレゼンで、どうやってユーモアを生かせばいいのでしょうか?
スピーチ・プレゼンにおいてのユーモアとジョークの違いは、目的の違い、にあります。
ジョークは笑わせることが目的。一方でユーモアはメッセージを伝えることが目的の大前提で、そのうえで、緊張を和ませる表現で笑いにつなげる手法です。スピーチ・プレゼンの中で、笑わせるためだけのジョークを使ったら、本題に入った途端に、話の流れに溝を作ってしまうことになります。つまり、話している内容が、ただ点在している状態で、話が線として流れていきません。更にジョークはお笑い芸人さんのような高度なテクニックがないと失敗します。
大谷選手のこのスピーチでは「言わなくていいかな」とちょっと緊張感が漂ったところで、本音をユーモアで表現したことで、緊張を緩和する効果がありました。不快感どころか親近感さえ沸きましたよね。また、声のトーンも軽やかだったので、ユーモアがしっかりとユーモアとして効果的に「伝わる」ことに繋がりました。
ユーモア遣いの達人と言えば、イチロー選手です。
殿堂入りした際のスピーチを見てみましょう。日本語訳がついている動画を選んでみました。
イチロー選手が3人の元チームメイトについてエピソードを語るのですが、3人目の、「ジェイミ~!!!」というトーンからして、すでにユーモアが感じられ、そのあと面白そうなエピソードが来るのだろう、と期待がそそられます。
ジェイミ~~~!
君はレフトの守備はクレバーだが
ものすごくおしゃべりだ。(観客から爆笑)
初めて会ったとき、君は私に英語で30分も話し続けました。
でも私は何を言っているのか全く分かりませんでした。(観客から爆笑)
今、私の英語は少し上達しましたが、
まだ君の言っていることがほとんどわかりません。(観客も3人の元チームメイトも大爆笑)
ジェイミーとの仲の良さ、そしてジェイミーの人柄がとてもよく伝わってくるミニエピソードですが、ユーモアを使ったことでそれがより一層伝わってきました。
3.自然体な「自分のことば」
このイチロー選手のスピーチでは、冒頭で、”What’s up, Seattle!!!(シアトルのみんな、調子はどう?!というイメージでしょうか)”と勢いよくカジュアルな会話調で始まりました。
大谷選手も、常にカジュアルな会話調で話しています。
スピーチやプレゼンとなると、急に原稿を用意し、書き言葉をそのまま読んでしまう、という方も多いのではないでしょうか。
つい先日は、30分のプレゼンのすべてを原稿に起こし、まさに書き言葉のまま読み上げ続けた方がいらっしゃいました。
書き言葉と話し言葉は違います。
スピーチ・プレゼンは、「話す」コミュニケーションです。書いたものを読むだけなら、誰にでもできますし、また、わざわざあなたの話を聞きに来てくださった方にとっては、「なんだ読んでるだけか」、とがっかりしてしまう事でしょう。書き言葉を読んでいると、それは相手にすぐに伝わります。たとえそれを丸暗記したとしても、書き言葉だと、話し言葉としては不自然だったり硬すぎたりするものですから、やはり相手にすぐ伝わります。その結果、心で通じ合えず、共感を得ることなどは当然できないでしょう。
Hallway Test”廊下テスト”
でもスピーチ原稿を書き慣れていないと、つい、書き言葉で書いてしまいがちです。
そこで、一度原稿を書いたら、あるいは書き進めながら、私が、”Hallway Test(廊下テスト)”と呼んでいるテストにかけてみてください。
例えば、まず原稿にはこう書いたとします。
「皆さんは、調査分析は時間がかかり、細かい作業で面倒だ、と思う方もいらっしゃるのではないでしょうか。」
皆さんは今この記事を読んでいますから、違和感なく読めることと思います。
ではこれを”Hallway Test(廊下テスト)”けてみましょう。
廊下で誰か一人とすれ違ったとします。鈴木さんだとしましょう。鈴木さんに話しかけるなら、なんと言うでしょうか?
上記のような言葉遣いは決してしないはずです。
おそらくこんな言い方をするんではないでしょうか。
「調査分析、時間もかかるし細かい作業で面倒、と思いませんか?」
自然な会話口調になりましたね?
これが”Hallway Test(廊下テスト)”です。
スピーチ・プレゼンは読むものではなく、耳で聴くものです。
自分らしい言葉、つまり、自分が普段使うような会話口調で話しかけることで、聞き手も親近感を持ってくれます。
是非、”Hallway Test(廊下テスト)”でチェックをしてみてください。
「聞き手視点」、「ユーモア」、「自分のことば」。
大谷選手やイチロー選手のスピーチから是非、マネしてみたい3つのポイントですね。
🔸ユーモアについて詳しく知りたい方はこちら:
🔸イチロー選手の緊張対策:
大勢の前でのスピーチはプロでも緊張する。でもそんな時には、まず深呼吸。そして今の自分に集中すること。会話を楽しむがごとく聴衆とスピーチすることで普段の実力を発揮できるだろう。さらには、準備を十分にし、セルフイメージ、マインドセットを書き換えよう。
🔸日本人が世界で活躍するにはスピーチの習得は必須:
英語は単なるツールに過ぎず、グローバルな成功にはスピーチやプレゼンテーションのスキルが不可欠だ。弊社のブレイクスルー・スピーキング ウエビナー基礎コースは、異文化理解を含む効果的なコミュニケーション力が身につけられる。きっとあなたの国際舞台での活躍の手助けになるだろう。
🔸イチロー選手のようなスピーチをしてみたいとお考えのあなたに:
スピーチ学習は、あなたの人生や仕事の質を劇的に変えるものなので、ここに思い切って自己投資することは大いに意味があることだ。どのスピーチ講座が自分にぴったりなのかを選ぶためにはは、自分のニーズ・目的・価値観をクリアにした上で、比較検討し、自分のレベルに合わせたものを選ぶのが賢明なやり方だ
🔸インタビュー対策:即興でしゃべる時のコツとは?
即興スピーチで成功するコツは、機会を作って練習し、場慣れしておくこと。質問を想定し準備する。パターンを覚えてそれにスピーチを当てはめる訓練。最初に頭に浮かんだ直感を信じてそのトピックを話すこと。一つのメッセージを明確に、具体的に語ること、が重要になる。