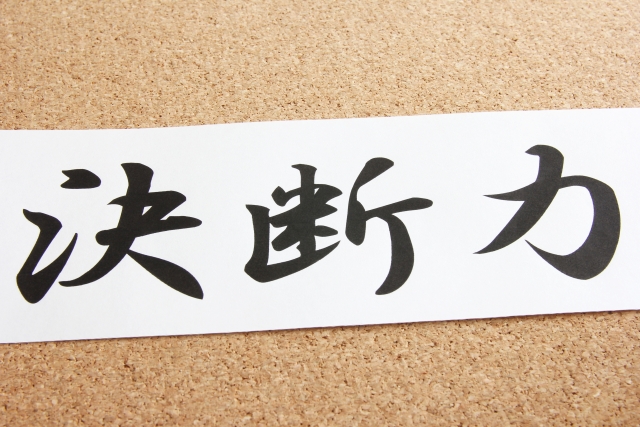あなたは最近、こんなふうに迷ってしまった経験はないだろうか。 「チャンスだとは思うけれど、どう決断すべきか分からない…」 「意見を求められたのに、判断がつかず黙ってしまった…」
実は今、多くの人が“決断のむずかしさ”に直面している。
ロシアの戦争、コロナの流行、物価高、AIによる急激な変化。。。 これらの影響により、将来の予測が困難な”VUCA時代”(Volatility:変動性、Uncertainty:不確実性、Complexity:複雑性、Ambiguity:曖昧性)に私たちは生きている。そして、こんな時代だからこそ、今、最も求められているスキルの一つが「意思決定力」なのだ。
この記事では、意思決定力とは何か、それが今なぜ必要なのか、そしてあなた自身がその力をどう高めていけるのかを、6つの方法を中心に、わかりやすく紹介していく。(意思決定力とマネジメントには深い関連性があるが、マネジメント全体についてはこちらの記事を参照されたい)
この記事の内容
意思決定力とは?
意思決定力とは、選択肢の中から最適なものを選び、行動に移す力である。 特徴的なのは、「正解のない問い」に対して、自らの価値観や経験も総動員して決断するという点だ。これは個人や組織が日常的に直面するさまざまな決定に関わる重要なスキルだ。意思決定力を持つ人は、情報を収集し分析し、その情報をもとに未来の結果を予測して、最良の選択をすることができる。決断する際の根拠には、客観的データに加えて、本人の経験や直感といった主観的な要素まで含まれる。そのため、選択肢が多かったり、大きなリスクを伴うほど、迷いが生じやすくなる。だから、決断には、覚悟と勇気、責任が求められる。
判断力との違い
似ている言葉に「判断力」があるが、両者には明確な違いがある。
判断力
与えられた情報を客観的に分析し、選択肢のメリット・デメリットを比較する力。
判断力は客観的データや論理を用いるが、判断力による結論は誰もが同じになるという再現性がある。
判断力のある人は、情報を客観的に分析し、選択肢の長期的な結果や影響を予測する能力がある。判断力はより深い分析や長期的な視点が求められる状況で重要であり、情報の評価や選択肢の影響を理解する点が特徴だ。
意思決定力
分析の結果を受けて、覚悟を持って選択肢を選び、行動に移す力。
一方で、意思決定力は、複数の選択肢の中から1つを選び、実際の行動に移す能力を指す。意思決定力のある人は、選択肢を検討し、その中から最適なものを選んで迅速かつ自信を持って行動する。意思決定力には主観的な要素も根拠とする点が異なる。その人にしか出せない結論でもあり、決断する人によっては結果が異なる場合も多い。
簡潔に言えば、意思決定力は行動への移行力を指し、判断力は情報の評価や選択肢の分析力を指す。両者は意思決定プロセスの異なる段階で発揮されるスキルであり、バランスを取りながら使うことで、より効果的な意思決定が可能となる。
なぜ今、意思決定力が求められているのか?
1 先の読めない時代の羅針盤になるから
現代は、今までの価値観では判断できない時代と呼ばれ、常に新しく生まれ変わっている変遷の時代だ。こんな情勢の中でビジネス・自分のプロジェクトを発展させていくためには、将来の方向性やビジョンを明確にし、組織全体に浸透させ、全員で実行させていく必要がある。 この際に指針となるのは、リーダーによる意思決定力だ。 チームがリーダーの決断を尊重し、信頼するためには、遅れたりためらったりすることなく、迅速で適切な決定が求められる。別にリーダーだけの意思決定力だけを頼りにしなくとも良い。今は、メンバー一人ひとりの前向きな姿勢・考え方がチームを支え、プロジェクトを推進する力になる。どんなことに対しても「他人事ではなく、自分ごと」として考え、「自分だったらこうする」という、一人ひとりの意思決定力が大きな意味を持つだろう。
2 変化・競争が激しい現場で、素早く打ち手を出せるから
ビジネスや日常生活において、急な状況変化や緊急事態が発生することがある。また、 競争の激しいビジネス環境では、選択肢を早く評価し、競合他社よりも先に新しい戦略やアイデアを実行することが成功の鍵となる。このような場面では迅速な意思決定が求められ、適切なアクションを選択し実行する能力が必要であり、市場での優位性を確保できる可能性が高まる。
3 チャンスを逃さず、成功の確率を上げられるから
有望な機会やアイデアが現れた際に、迅速に行動しなければ逃してしまうことがある。適切な決断を下し、早期に行動することで、成功へのチャンスを最大限に活かすことができる。
4 問題を放置せず、早期に解決へ導けるから
問題解決においても、適切な決断は重要。問題が放置されると、それが他の分野に波及して、返って問題が複雑化してしまうことがある。早期に適切な対応を取ることで、問題を効率的に解決できる。
このように、現代における意思決定力は、「結果を生み出す力」として非常に重要なのだ。
意思決定能力が備わっている人の特徴
<チェックリスト>
- □ 自分なりの判断基準やビジョンを持っている
- □ ゴールが明確で、選択肢の優先順位を決められる
- □ 情報をもとに、即断即決と熟考のバランスをとれる
- □ 状況の変化に柔軟に対応できる
- □ 勇気と自信を持って一歩を踏み出せる
あなたには、いくつ当てはまっただろうか? この力は、特別な才能ではない。正しい方法で鍛えることで、誰でも伸ばすことができる。それぞれの特徴について解説しよう。
1. 自身の判断基準を持っている
意思決定力のある人々は、自身の判断基準やビジョンを持っていることが特徴だ。情報が完璧に揃わない場面でも、現状の情報を元に独自の基準で決断し、その結果に責任を持つことができる。
2. ゴールが明確で、選択肢の優先順位を決められる
目標や優先順位が明確な人ほど、決断力を発揮しやすい。曖昧な目標では正しい意思決定は難しいだろう。さらに、目標や戦略に基づいて、重要な課題と細かな詳細を区別・整理することができ、選択肢の優先順位を明確に設定できる。その結果、確かな判断を下すことができるのだ。
3. 情報をもとに、即断即決と熟考のバランスをとれる
意思決定力が高い人は、状況に応じて即座に判断することも、じっくり検討してから決断することもできる。また、周囲の状況を把握しつつ的確に行動できる。頭の回転が早い人とも言える。
適切なタイミングで決断を下すために、情報の収集と分析に過度に時間をかけず、タイムリーな行動を取れる。また、複雑な情報や状況を分析し、本質的なポイントを見極められ、重要な情報を素早く見抜くことができる。また、データや情報を客観的に評価し、深い理解を持って意思決定に反映することができる。ちなみに、頭の回転は訓練すればいくらでも早くなれる。
4. 状況の変化に柔軟に対応できる
迅速な決断を下す一方で、状況が刻々と変わる際にも柔軟に対応できる。過去の決断に固執せず、新たな情報を組み入れながら、変化に臨機応変に対応し、適切な修正を行うことができる。さらに、外部環境や内部状況に対する感受性が高く、それに基づいて意思決定を行うことができる。一つの考え方に囚われてしまう人、頑固な人はこういう対応が難しい。
5. 勇気と自信を持って一歩を踏み出せる
勇気と自信が最初からある人など誰もいない。勇気と自信があるように見える人は、多くの失敗を経験した人たちだ。それ故、失敗は一時的な通過点であり、そこから学ぶことを知っている。だから、失敗を必要以上に恐れることがない。ワクワクしながら、挑戦的な態度で行動することができる。成功と失敗のリスクを受け入れ、自信と勇気をを持って進むことができる。
- 過去の成功や失敗から得た教訓を活かし、次の意思決定に反映させられる。
- 自分の意思決定に対して責任を持ち、その結果を受け入れる用意がある。
- ポジティブな結果だけでなく、失敗にも立ち向かい、学びと成長に繋げられる。
これらの特徴が組み合わさることで、意思決定力のある人は複雑な状況でも自信を持って適切な判断を下し、結果を導くことができるのだと思う。
意思決定力を高める6つの方法
意思決定スキルには、以下の側面を含んでいる。それぞれについて、どうしたらその力を強化できるか、一つひとつ見ていこう。
- 情報収集力と分析力を鍛える
- 選択肢を評価する力を養う
- リスクを見極める目を持つ
- 優先順位をつける癖をつける
- 迅速な判断力を磨く
- コミュニケーションで、周囲を巻き込む
1 情報収集力と分析力を鍛える
😄主観だけに頼らず、信頼できる情報を幅広く集める
ニュースや業界誌、専門書籍など複数の情報源から情報を取得する習慣をつける。Googleアラートなどで関心テーマの最新情報を自動収集すると便利。フェイクニュースや誤情報を見極めるために、ファクトチェックサイトや一次情報の確認を心がけることが大切だ。
😄日常からデータ整理やパターン認識の練習をする
家計簿や日報、アンケート結果など身近なデータを自分で整理・分析してみる。グラフ化やマインドマップ(かなりオススメ)などの可視化手法を取り入れ、傾向や因果関係に気づく力を養うといいだろう。
😄シミュレーションやロールプレイで判断経験を積む
過去のビジネスケースを題材に、架空の状況設定で「自分ならどう決断するか」を練習する。職場やチーム内で定期的にロールプレイ形式のケーススタディを実施し、フィードバックをもらう。例えば、「米の値上がり」のニュースを見ていて、自分が大手スーパーの社長だったら、どんな判断をするか考えてみて、実際の取り組みと比較してみる、など。。。
2 選択肢を評価する力を養う
😄メリット・デメリットを視覚化したり、SWOT分析や意思決定ツリーで比較検討する習慣をつける
それぞれの選択肢のメリット(期待される成果、コスト削減、スピード感など)とデメリット(リスク、コスト、人的負担、タイムロスなど)を具体的に書き出すことで、全体像を客観的に把握する。
例えば「A案は初期投資が少ないが、効果が出るまで時間がかかる」「B案は短期間で結果が出るが、失敗したときの影響が大きい」といったように、リスクとリターンのバランスを比較する練習を重ねる。このメリット・デメリットの整理を、マトリクス形式(縦軸と横軸に評価軸を取り、選択肢ごとの強みや弱みを視覚的に比較する表)や点数評価形式で行うことで、視覚的にも判断しやすくなる。
SWOT分析では、自分の強み(Strengths)、弱み(Weaknesses)、機会(Opportunities)、脅威(Threats)を洗い出し、選択肢がどの領域に強く作用するかを視覚化する練習をする。
意思決定ツリーでは、選択肢ごとの結果を枝分かれにして整理し、結果の確率やインパクトを数値で比較する習慣をつける。
😄他者の意見や専門知識を活用する
日頃から信頼できる同僚・先輩・上司に「自分の考えを話す」時間を設け、視点の違いを学ぶ。SNSや専門家の発信(書籍、講演、YouTube、noteなど)に触れ、様々な分野の思考法を取り入れる。ディスカッションやワークショップに参加し、他者と考え方をぶつけ合う経験を積む。複雑な問題に対しては、ブレインストーミングやディベートなどの方法を活用して、多角的な意見を収集する。
3. リスクを見極める目を持つ
意思決定には、リスクがつきものだ。リーダー・マネージャーは、各選択肢のリスクを評価し、可能なリスクを最小限に抑える方法を考える必要がある。リスク評価に基づいて、どの選択肢が最も確実であるかを判断することが求められる。
😄リスクマトリクスを使って影響度と確率を見える化
縦軸に「影響度(どれだけ被害が大きいか)」、横軸に「発生確率(どのくらいの確率で起きそうか)」を設定した表を作成し、各リスクをその中に分類する。これにより、どのリスクを優先して対処すべきかが一目でわかるようになる。例えば「高確率・高影響」の領域に入るリスクは、最優先で対策を講じる必要がある。
😄最悪のケースにも備えるバックアッププランを用意
重要な決定には、必ず代替案(Plan B、Plan C)を用意しておく。例えば新規プロジェクトの開始が延期になった場合のリソース配分計画、主要メンバーの離脱に備えた役割の再設定など。「想定外」を減らすために、事前にリスクシナリオを複数想定し、それぞれに対する対応策をシミュレーションしておくことが重要である。
4. 優先順位をつける癖をつける
複数の選択肢がある場合、それらを優先順位に従って整理する必要がある。どの選択肢が最も重要で、組織やチームの目標に最も合致するかを判断、決定しなくてはならない。
😄表面的な課題と本質的な問題を見分ける
表面的な課題と本質的な問題を見分けるには、 アイスバーグ原則を意識し、目の前に起きている現象だけで判断せず、その背後にある原因や構造に注目する必要がある。たとえば、会議での発言が少ないという表面的な課題があった場合、それは「話す機会が与えられていない」のか「心理的安全性が低い」のか、あるいは「議題が不明確で話しにくい」のかといった、深層の問題を掘り下げて見極める力が求められる。
😄目標と戦略に合致しているかどうかで選ぶ
また、意思決定を行う際には、その選択肢が自分や組織の中長期的な目標や戦略に本当に合致しているかを常に確認することが重要である。一時的な成果や目先の数字だけにとらわれず、「この選択は私たちが目指す未来像に沿っているか?」という視点を持ち、方向性と整合性のある選択を意識することが、ぶれない意思決定につながる。
5. 迅速な判断力を磨く
現代は、ある程度のスピード感を持って、プロジェクトを推進しなくてはならない。そうでないと、周りの社会の変化に対応できないことが多々ある。情報収集と分析を適切に行いながらも、状況に応じてスピーディな決断を下す能力が求められている。
😄完璧な情報を待つのではなく、今ある情報で動く
完全な情報が揃うのを待っていては、機を逃すことがある。そこで重要になるのが、「完璧な情報を待つのではなく、今ある情報で動く」という考え方である。たとえば、会議での意思決定や現場対応では、状況が刻一刻と変わる中で素早い判断が求められる。その際には、現時点で入手可能な情報を基に、一定の仮説を立てて行動を起こす勇気が必要だ。もし情報が不足していると感じたら、同時並行で追加情報を収集しつつ、軌道修正できるよう備えておけばよい。
😄過去の成功・失敗から素早く学び、次に活かす
また、過去の成功・失敗から素早く学び、次に活かす力も、迅速な判断には不可欠である。たとえば以前に類似の場面で成功した要因や、失敗した際の見落としを記録として残しておくことで、未来の判断材料としてすぐに引き出せるようになる。つまり、経験の「蓄積」と「活用」を習慣化することで、判断スピードは格段に上がっていくのだ。
6. コミュニケーションで、周囲を巻き込む
意思決定の過程と結果を関係者に適切に伝えることも重要だ。チームや関係者が決定の理由や根拠を理解し、共感できるようにすることで、組織が決定を受け入れやすいように配慮することもリーダー・マネージャーの役割だ。リーダーだけではない。何かを発案したり、起業したり、改革を推進するためには、コミュニケーション力がモノをいう。
😄決定の背景や理由を言語化し、周囲に納得してもらう
決定の背景や理由を言語化し、周囲に納得してもらう。たとえば、「なぜこの決断をしたのか」「何を優先した結果なのか」「どのような情報や価値観をもとに選んだのか」といった点を、自分の言葉で丁寧に説明することが大切である。これにより、チームメンバーや関係者がその判断を理解しやすくなり、自発的な協力や共感が生まれる。また、説明を通じて自分の思考を整理できるため、意思決定そのものの精度も高まる。
😄フィードバックを受け入れ、他者の視点を取り入れる
フィードバックを受け入れ、他者の視点を取り入れることは、意思決定の質をさらに高めるために欠かせない要素である。自分の考えに自信がある場合でも、第三者の目線からの意見によって見落としていたリスクや新たな可能性に気づくことがある。たとえば、会議の後に「この判断は納得感があるか」「誰かにとって不利益になっていないか」といった視点で周囲から率直な意見をもらうことで、より多角的でバランスの取れた判断が可能になる。また、フィードバックをただ受け入れるだけでなく、それに対して自分なりの解釈や問いを返すことで、対話の質も高まり、チームとしての合意形成も円滑に進むようになる。
現代は、先行きが不透明で予測が困難な時代だからこそ、意思決定力が求められ、そのスキルアップが望まれている。それは、変化に満ちている時代を生き抜くための重要な資質だ。意思決定力とは何か、どんな人がそれを持っているのか、その意思決定力を鍛えるための6つの方法を紹介する
実は「迷うこと」にも意味がある
迷わない人など誰もいない。人はみんな迷っている
「迷っている自分」に対して不安を抱く人は多いが、実はそれも大切なプロセスである。 私自身、「もうこれしかない」という感覚が訪れるまで、あえて決断を先送りすることもある。 迷っている時は、まだ時期尚早なのだ、と解釈する説があり、私はそれに賛成だ。決断とは自然に決まるものなのだと思う。決断の時は必ず来る。だから、それまで待つのが上策だと、今までの人生経験から思う。このやり方だと、ある時は、次々と決断を下したかと思うと、ある時は、全く動かない時もある、という風に人の目には映る。
しかし、それで他の人が全て納得するかは別問題だ。時には優柔不断だと非難されるかもしれない。だから、大切なのは、迷いの中でしっかりと情報を集め、分析し、選択肢を整理しておくこと。 そうすることで、決断の瞬間が訪れた時に、自信を持って一歩を踏み出すことができる。周りの人に分かりやすく説明するためにも、そして自分自身が納得したり、決断の時を気持ちよく迎えるためにも、情報の分析や選択肢の評価が必要になるし、リスク評価も必要になるし、優先順位の決定が必要になる。
▼関連記事:スピーチを通して学ぶコミュニケーション力
現代は、先行きが不透明で予測が困難な時代だからこそ、意思決定力が求められ、そのスキルアップが望まれている。それは、変化に満ちている時代を生き抜くための重要な資質だ。意思決定力とは何か、どんな人がそれを持っているのか、その意思決定力を鍛えるための6つの方法を紹介する
意思決定力・コミュニケーション力を鍛えるには?
1 オンラインセミナーや専門講座を活用しよう
意思決定力を高めるには、実はコミュニケーション能力を磨くことが大きなカギになる。自分の考えを明確に言語化し、相手にわかりやすく伝える力があると、意思決定の根拠を整理しやすくなり、他者の協力も得やすくなる。
“意思決定力を高めるセミナー“や“戦略的意思決定のためのワークショップ“など、意思決定スキルを強化するための専門的なセミナーやトレーニングが存在するので、活用してみるのもいいだろう。CourseraやUdemyなどのオンラインプラットフォームや、各種スピーチ教室でもコミュニケーション力をアップさせることができる。実践的な「伝える力」と「考える力」を育むトレーニングを受けることは、意思決定力の土台づくりに大いに役立つはずだ。
▼Web講座でスピーチ力を鍛えるには?
現代は、先行きが不透明で予測が困難な時代だからこそ、意思決定力が求められ、そのスキルアップが望まれている。それは、変化に満ちている時代を生き抜くための重要な資質だ。意思決定力とは何か、どんな人がそれを持っているのか、その意思決定力を鍛えるための6つの方法を紹介する
2 メンターやコーチに相談しよう
意思決定スキルを向上させるためには、経験を積むことや過去の意思決定の振り返りを行うことが役立つ。また、他の経験豊富な同僚やアドバイザーからのフィードバックを受けることも重要だ。その時々の意思決定は常に完璧ではないかもしれないが、適切な情報と分析、そして前向きな姿勢を持つことで、より完全なものへと近づけることができるだろう。
そういう意味で、経験豊富なメンターやコーチにアドバイスを求めることは、実践的な指導を受けられる絶好の機会だ。彼らからのフィードバックやアドバイスは、意思決定スキルの向上に大きな助けとなるだろう。
現代は、先行きが不透明で予測が困難な時代だからこそ、意思決定力が求められ、そのスキルアップが望まれている。それは、変化に満ちている時代を生き抜くための重要な資質だ。意思決定力とは何か、どんな人がそれを持っているのか、その意思決定力を鍛えるための6つの方法を紹介する
現代は、先行きが不透明で予測が困難な時代だからこそ、意思決定力が求められ、そのスキルアップが望まれている。それは、変化に満ちている時代を生き抜くための重要な資質だ。意思決定力とは何か、どんな人がそれを持っているのか、その意思決定力を鍛えるための6つの方法を紹介する
3. 過去の意思決定を振り返る習慣を持とう
成功も失敗も、宝の山だ。過去の出来事に対する自分の意思決定が適切なものだったか、それを振り返ることによって、自分の「判断の癖」が見えてくるというもの。日記をつけることも決断力を高めることにつながるかもしれない。
まとめ:意思決定力・決断力は“後天的に”伸ばせるスキル
意思決定力は、特別な才能ではなく「鍛えられるスキル」である。 そして、その鍵は「情報を整理する力」と「一歩を踏み出す勇気」の掛け算にある。だからこそ私は、意思決定力を鍛えたいあなたに、スピーチやプレゼンの学びを強くおすすめしたい。 声に出して考えを伝える習慣は、まさに決断力を鍛える最高のトレーニングなのだ。