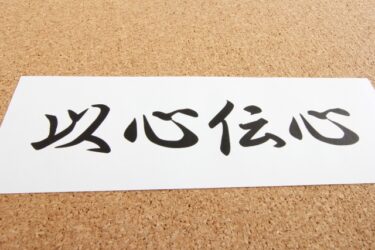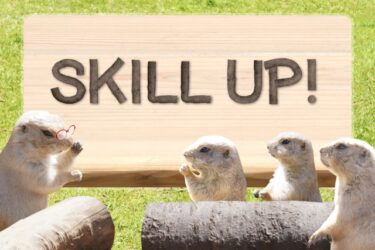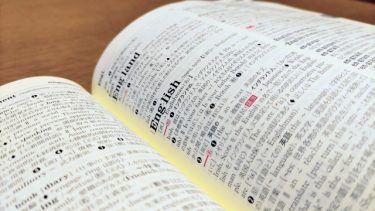この記事の内容
ハーバード大生にインパクトを与えた楽天・社内英語化のメリットとは
社内公用語英語化の珍しい成功事例
2010年、楽天は社内の公用語を全て英語に統一することを宣言し、2年間の移行期間を経て、その体制を整えた。これに対して、過剰反応したり、戸惑ったりする人も多いだろう。日本人特有の異常とも言える英語苦手意識や、日本人同士で英語を話すことの違和感からそんなリアクションになってしまう。だが、楽天の事例は、そんな国民性を尻目に英語化を一気にやり遂げた珍しいケースとして、米国ハーバード大学経営大学院で教材として取り上げられている。(佐藤智恵著「ハーバードでいちばん人気の国・日本」p182より)
楽天にとっては好都合なことが多かった。英語が公用語になることで、メリットとして次の二点が挙げられる。
- コミュニケーションが円滑に進み、作業が効率化した。
- 社員が世界中のリソース(人材、資金、情報)を共有できた。
楽天という企業の業態や文化にうまく英語が溶け込んだのだと思う。ちなみに、楽天は英語化を導入して5年後、TOEICの社員平均点が526点から814点まで上昇したという(楽天公式ウエブ)。日本人は英語が苦手と言われるが、日本人でも徹底して実践すれば立派にできることを、彼らは証明してくれた。
楽天の英語化をみんな真似すべきか? 社内英語化のデメリットとは
社内公用語英語化3つのデメリット
一方で、社内公用語英語化にはデメリットもある。
1.導入への大きな負担
英語化は、組織にも社員にも大きな負担がかかる。実際にうまく動き出すには時間もかかるし、相応のお金や人材を投資しなくてはならない。楽天も宣言から実際にスタートさせるまでに、2年の試行期間を費やしている。
2.変化による混乱の発生
さらに、英語化によって企業文化が変わると、混乱を生むことがしばしばあり、場合によっては辞職する社員も出るだろう。
3.問題対応への時間やコスト
異文化間での摩擦の発生はつきもの。その時に備えて、対応できるシステムや人材は常に必要だ。法的なビザの対応などもある。
楽天のように、社員全員に対して英語習得を要求するのは、日本だけではなく、英語を母国語としない国々では、かなりハードルが高いかもしれない。
管理職のみ英語化して成功したEU・真のグローバル化とは
実際、多言語文化を背景に持つヨーロッパでは、管理職のみ公用語を英語化して成功したという企業の例もある。楽天がうまく行ったからと言って、そのマネをすることだけがグローバル化成功への鍵とは限らない。
「英語化」イコール「グローバル化」とは限らない
英語を話すことが、そのまま直接グローバル化に繋がると誤解する人が多いが、それは大きな誤解だ。英語だけ取り入れても、国際的なコミュニケーション方法を学ばなかったら意味がない。英語を通してそのコツを学ぶのが目的なのだ。英語(言語)は意思疎通のためのツールの一つにすぎない。英語が広く使用されているから、たまたま英語が便利なだけであって、状況によっては他の言語の方が優位な場合もある。しかし、英語を練習することで、なんとなく国際人になったような気になってしまう。日本人の英語コンプレックスがそうさせてしまうのか。そこが失敗の罠なのかもしれない。人、カネ、モノ、経済における国際コミュニケーションのコツは、わざわざ外国語を習うまでもなく、母国語を通してでも習得できる。その方が負担が少なくてすむだろう。
言葉自体よりも円滑なコミュニケーションがカギ
グローバル企業トヨタの公用語は日本語
確かに、英語の方が世界中のリソースにアクセスしやすいことは事実だ。しかし、例えば、日本を代表するグローバル企業であるトヨタの公用語は日本語だ。だから「カイゼン」などの日本語が国際標準として使われるようになった。トヨタのように社内に独自のノウハウがあり、それが日本の文化によって醸成されたものなら、日本語を公用語にした方がその真髄が伝わりやすく、組織体としての強みをより発揮しやすくなるだろう。
真のグローバル化に必要なこととは?
くどいようだが、グローバル化のポイントは、外国人を含む社内のコミュニケーションを円滑にすることであって、英語を話すことではない。楽天のように英語を手段として成功すればよいが、リスクも大きい。日本語でも十分同じ目的が達成されることは、トヨタが示してくれている。
とは言っても、別のノウハウが必要になる。だから、外国人とのコミュニケーションを日本語で円滑に行うためには、どうするのがベストなのか。そこに集中し、自社、そして自分自身の「カイゼン」を追求し、試行錯誤することが、真のグローバル化への早道だと思う。
外国人との円滑なコミュニケーションの具体的なノウハウについては、以下の記事を参照してほしい。なお、弊社が提供する「ブレイクスルーメソッド基礎コース」でも、異文化コミュニケーションのコツについてより深く詳しく学ぶことができる。
外国人を含む社内のコミュニケーションを円滑にするコツ
■円滑な異文化間コミュニケーションのノウハウ記事5選
日本では、非言語的なコミュニケーション(ジェスチャー・顔の表情など)に依存する場面が多いのに、実は、多くの人がこのことを認識しないままでいる。これも当たり前すぎて、普段あまり意識することがないことの一つだ。非言語的であるが故に、これを言語化するのはかなり難しい作業だと言える。ぜひ、次の5つの記事を参考にされたい。
①誤解を避け外国人と円滑に話すためのコツ
非言語コミュニケーションには多くの利点があると同時に、それが効果的に使われないと多くの誤解を生む温床にもなる。言語と非言語コミュニケーションの違いを理解し、うまく組み合わせることで、よりスムースな異文化間コミュニケーションが取れるようになる
②コミュニケーションギャップを解消するための詳細ステップを解説
文化の違いを認識し、それを深く理解し、状況に応じて臨機応変に対応することで、異文化間における誤解が避けられる。まずはどんな違いがあるのかを学習しよう。
③日本人特有の「言わぬが花」
言うべきか、言わざるべきかの選択は日米のコミュニケーション上では違いがある。日本は「言わない」という選択をし、アメリカでは「すべて言う」という選択をする。その文化的な違いを理解した上で対策を考え、意思疎通を図ることで誤解なくスムースな相互理解が得られることだろう
④沈黙が誤解を生む温床に?!
沈黙に対する価値の重さは日米比較すると、日本の方がはるかに大きい。その違いからくる誤解がある。アメリカ人からの質問に日本人が沈黙してしまうと侮辱ととられてしまう。何かしら言葉に出して、十分に説明する努力が必要だ。
⑤あなたのちょっとした顔の表情にも意識を向けよう!
日米の顔のしぐさ・表情による表現方法の差は大きく、お互いの理解の妨げになることがある。だから、お互いの文化の違いをよく理解して、リハーサルを十分にしてから、スピーチ・プレゼンをすることで誤解を避け、あなたの真意が相手に伝わるように努めたい。
■国際コミュニケーションのために、まず自国の言語・文化を知る記事5選
欧米でははっきり表現しても、日本では、あまり表現しないものがある。これはコミュニケーションをとるにあたって障害になるので、ぜひ知っていて欲しい。次の5つの記事を参考にされたい。
①”I love you”は訳せない。沈黙が美徳の日本人
日本人は、古くから言葉以外のもの(表情・ジェスチャーなど)に頼ってコミュニケーションをとってきた。だから、言語に強く依存してコミュニケーションをとる文化圏から来た外国人と話すときに誤解が生じやすい。日本人が外国人と話す時は、以心伝心に頼らないで、できるだけ思っていることを言葉で表すことが重要だ。
②日本語の文法「省略」がコミュニケーションを妨げる?!
日本語には「当たり前」な部分は省略される性質があり、これは文法的な機能であり、仕方のないこと。しかし、それが論理思考に影響することを認識することが大切だ。なぜなら、それを意識することで、より分かりやすい英文を書くことができ、外国人とのコミュニケーションがよりスムースになるからだ。
③自分を戒める日本文化
西洋では「コップが壊れました」と言うところを、日本人は「コップを壊しました」と言う傾向が強い。「壊した」と言うことで謝罪の意味を込めているのだ。こういう謝罪を尊ぶ姿勢がもう少し世界に広がってもよいのではないか。それには日本人自身がその違いをはっきりと認識し、言葉で表し、説明する必要がある。
④「つまらないもの」と言ってお土産を渡すのはなぜか?
日本人が贈り物を渡す時に言う「つまらないものですが」は、「これは取るに足らないものなので、お返しの心配はいらない」と言う意味だ。「恩知らず」にならないように心がける日本人は、ついお返しをしたくなるので、そんな相手を気遣う習慣から自然に生まれた言葉だ。何気ない日本語の裏側には、実は愛があふれている。
⑤英語中級者はご注意:「英語に敬語がない」は間違い!
日本人の英語はストレートすぎて相手を不快にする場合がある。英語にも敬語表現があることを理解し、深く学習し、ビジネスシーンで活用することでより厚い信用が得られる。だからと言って、間違いを恐れて消極的になるのではなく、間違いこそが英語上達のコツだと理解したい。
■グローバル人材らしい行動とは? コミュニケーション戦略に役立つ具体的な内容記事6選!
相手のことを知り、その戦略を立て、それを行動にうつすには、次の6つの記事が参考になる。
①「後で個人的に話をしよう」と考えると大問題に発展する可能性が大!
日本人の謙虚な姿勢は、欧米人で囲まれた会議では、誤解されやすい。それを避けるためには、必要以上にうなずかない、持ち帰らずにその場で意見を言う、などの努力が必要だ。また、そういう日本人としての特徴をあらかじめ会議のメンバーに伝えて理解してもらう努力も効果的だろう。
②アメリカ人にはネガティブな内容でも直接ぶつけよう!
沈黙をネガティブに捉えがちなアメリカ人に対して円滑な人間関係を築くには、「言わぬが花」ではなく、本人にとって耳の痛い内容でもいいので常にフィードバックしてあげることが大切だ。逆に、切りたい人材にはフィードバックをしなければいい。自然とやる気を失い辞めていくだろう。
③助動詞(仮定法)を正しく使えば、日本的な微妙な表現も可能に!
英語の Would は、単なる Will の過去形ではなく、仮定法である場合が多く、ありえないことだという前提で語っている場合がある。重要な交渉などでは、そのニュアンスはよく注意して読み取る必要があり、日頃から意識してこういう使い方には慣れておきたい。
④ちょっとした工夫で交渉がスムースに
上辺だけの英語にとらわれて、本当の相手の気持ちを汲まないと異文化間コミュニケーションは成り立たない。変に相手に迎合せず、状況に応じ、自分らしさや日本人として誇りを持ち、気持ちを豊かに表現できるのが真の国際人だと言えるだろう。
⑤「これは使える!!」ーーNoと言わずにNoを言う方法
ストレートに表現するだけが英語ではない。英語にも日本人的な言い回しがある。例えば、何か感じ良くソフトに断りたい時は、"I wish I could."(残念ながら…)を使ってみよう。柔らかく丁寧で、しかも断る意志がハッキリ伝わる、まさに日本人の心にぴったりくる断り表現だ。
⑥スピーチ・プレゼンでは論理的に述べよ!
あなたの意図が伝わらないのは、日本人特有の「省略」が原因であり、その省略によって論旨がストレートに進まない。英語を学習する前に、日本語でいいから、ロジカルに、ストレートに論旨を運ぶ訓練をしよう。そうすればあなたの英語力も、外国人とのコミュニケーション能力も飛躍的に向上するだろう。
■異文化コミュニケーションを深く詳しく学ぶならこちら:
日本人に欠けているものを補うのがブレイクスルーメソッドだ。スピーチをするに当たって、受講者がそれまで考えたこともなかったような視点、やるべきことが多く学べる。「相手の心に響くにはどうすべきか」について、失敗を繰り返し経験した講師たちが懇切丁寧に教えてくれ、自分だけでは気づけない気づきを与えてくれる