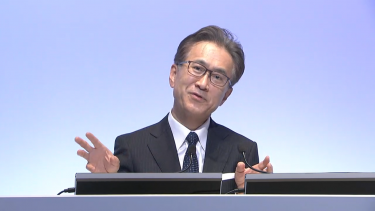投資家の態度を変えた魔法
大阪のプラスチック会社プロジェクトリーダー鈴木さんの場合
大阪のプラスチック会社に勤める鈴木俊介(仮名・38歳)さんは、新しいプロジェクトリーダーだ。このプロジェクトには投資家を募らないといけない。でも、彼はプレゼンが苦手だというので、いくつかの説明会に同行させてもらった。
質問もオファーもない、最初のプレゼン
最初のプレゼン。普通に挨拶をして自己紹介をした鈴木さん。会社概要・これまでの足取りをまず説明した後、セールスポイントである自社の強みを詳しく説明した。しかし、それは話が始まってから15分後だった。終了後、なんの質問もなく、オファーも全くなかった。
私はこれではまずいと思い、「鈴木さん、プレゼンの構成を少し変えてみませんか」と提案した。突然の変更に戸惑った彼だったが、「話の順番以外何も変えなくて良いから」との私の説得に応じ、2回目のプレゼンに臨んだ。
5つのオファーにつながった2回目のプレゼン
彼は、スピーチ冒頭からこう切り出した。
「わが社のプラスチックは生分解性であり、しかも、生鮮食品を保存する場合、通常よりも約3−5日以上は長く新鮮さを維持できます。それを可能にする特殊な微生物を加工する新しい技術を開発しました」
彼の話ぶりは相変わらずで、正直、お世辞にもうまいとは言えなかった。しかし、眠そうに聞いていた投資家たちは、一瞬目を見開いて注目し、聞き続けた。その後、質問が相次ぎ、最終的に「もっと詳しい話を聞きたい」というオファーが5つほどあった。
彼のしたことは、ただ、最初のプレゼンで、開始15分後にしたセールスポイントの説明(結論)を、冒頭に持ってきただけだった。
このエピソードからは、たくさんの学びがある。ただ話の順序を変えただけでこうも投資家の反応が違ったのは、それだけオープニングが重要だ、ということだ。
投資家の心を鷲掴みにするオープニング3つのポイント
- 「7秒ー30秒ルール」を使う
- ポイントを具体的に簡潔に述べる
- 話は下手でも誠実さは伝わる
1、「7秒ー30秒ルール」を使い、数秒間に興味を引く
- 失敗(最初のプレゼン)「自己紹介と会社概要」から始める。
↓ - 成功(2回目のプレゼン)「自社の強みと一番のセールスポイント」から話し始める。
聞き手は、聞き始めてから7秒でスピーカーであるあなたの印象を決め、30秒であなたの話に興味があるかどうかを判断する、と言われている。
最初のプレゼンでは、自己紹介、会社概要から始まった。これだとお決まりのパターンで面白味がない。加えて、鈴木さんは話し下手だ。この手のプレゼンを聞き慣れている投資家達にとっては、特に際立った所がない、ありきたりの、つまらない話だと思われたに違いない。
2回目では、冒頭に自社の強み、一番のセールスポイントを持ってきたことにより、聞き手に「面白そうだ。儲かるかも」という印象を与え、「よし話を聞いてみよう」という気にさせた。一度やる気が出れば、話が下手でも、最後まで聞いてくれる。なぜなら、投資家は、将来利益をもたらしそうならどんな話でも聞こうとするからだ。
スピーチやプレゼンなど人前で話す時、挨拶から始めていませんか?人前で話す場合、皆さんつかみや締めについて考えると思います。ご紹介する手法を活用することで、質の高いスピーチとなります。効果的なオープニングとクロージング手法について学び、結果につながるものにしましょう。
2、ポイントを具体的に簡潔に述べる
冒頭に持ってくることによって、鈴木さんは、違和感がないようにポイントだけを自然と簡潔に述べることができた。そうやって、一度オープニングで聞き手の注意を引きつけたら、あとで挨拶や自己紹介してもいいのだ。主催者へのお礼も話の途中で述べても別に問題ない。
聞き手も、忙しい投資家たちだ。彼らは自分が損しないように普段からいろんな勉強をしていて、知識も豊富だ。キーワードを言えば、大抵のことはわかってくれる。時間もない彼らは、要点だけを知りたいと思うものだ。
3、話は下手でも誠実さは伝わる
あまりプレゼンがうますぎるのも、実は考えもの。上辺の話ばっかりで本当は中身がないと思われてしまう節もある。やりすぎには注意が必要。だからと言って、下手のままでは見向きもされない。
しかし、この場合の鈴木さんのあり方は、逆に相手に誠実さを感じさせた。それを可能にしたのは、オープニングでのちょっとした工夫だったわけだ。下手でも、一生懸命工夫すれば、それは好感を持って受け入れられるものだ。
スピーチの成功は準備にかかっている。準備の努力が8割と言っても過言ではない。まず聴衆の調査・分析から始まり、シンプルな構成を考え、入念にリハーサルを行う。こうすることで緊張することなく、相手の心に響き、分かりやすく、誰にでも受け入れてもらえるスピーチができるだろう
あがり症を克服するには、心理面と技術面でのアプローチが重要だ。心理面では、イメージトレーニングで自分の思い込みを取り除き、スピーチに対する新しいセルフイメージを構築しよう。技術面では、スピーチの準備に時間をかけたり、構成を工夫したり、当日のとっさの対策をトレーニングすることで、必ず克服できる。
スピーチの上達で埋れた技術に真の評価をもたらせ!
日本には多くの優れた技術が存在するのに、逆にそういう会社ほど埋れてしまっているとよく言われる。本当にもったいない話だ。
しかし、ただほんの少しプレゼンの構成を変えるだけで、チャンスが生まれる可能性は大いにあると思う。特にオープニングは大切だ。
たとえ今まで過小評価されていたとしても、もっともっとスピーチのやり方を研究することで、スポットライトを浴びて世界で活躍できる会社・人材は増えるだろう。
■短時間でプレゼンする時に役立つ記事はこちら
超多忙な人に対するプレゼンは3分でまとめよう。それには、頭の中にある情報をすべて書き出して、その中から一番重要なメッセージ(ワンビックメッセージ)は何かを抽出するプロセスが重要だ
■併せて読みたい! 沈黙が誤解を生む?!
沈黙に対する価値の重さは日米比較すると、日本の方がはるかに大きい。その違いからくる誤解がある。アメリカ人からの質問に日本人が沈黙してしまうと侮辱ととられてしまう。何かしら言葉に出して、十分に説明する努力が必要だ。
■併せて読みたい! 文化の壁を乗り越えるための4ステップ
スピーチの上達には、聴衆に対する理解が欠かせない。ましてやグローバルな舞台で活躍するには、異文化に対する理解とそれに伴った行動ができる人材が必須だ。自身の文化・言語に対する認識はもちろん、相手の文化・言語に対しての知識、観察、理解を通して、その対策を計画的に練り、調整しながらそれを行動に移すことができるかどうかがポイントになる。
■併せて読みたい! グローバルな場面で誤解を避けるコツ
文化の違いを認識し、それを深く理解し、状況に応じて臨機応変に対応することで、異文化間における誤解が避けられる。まずはどんな違いがあるのかを学習しよう。